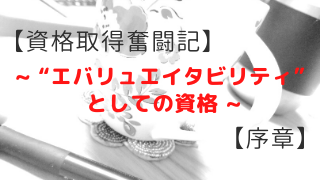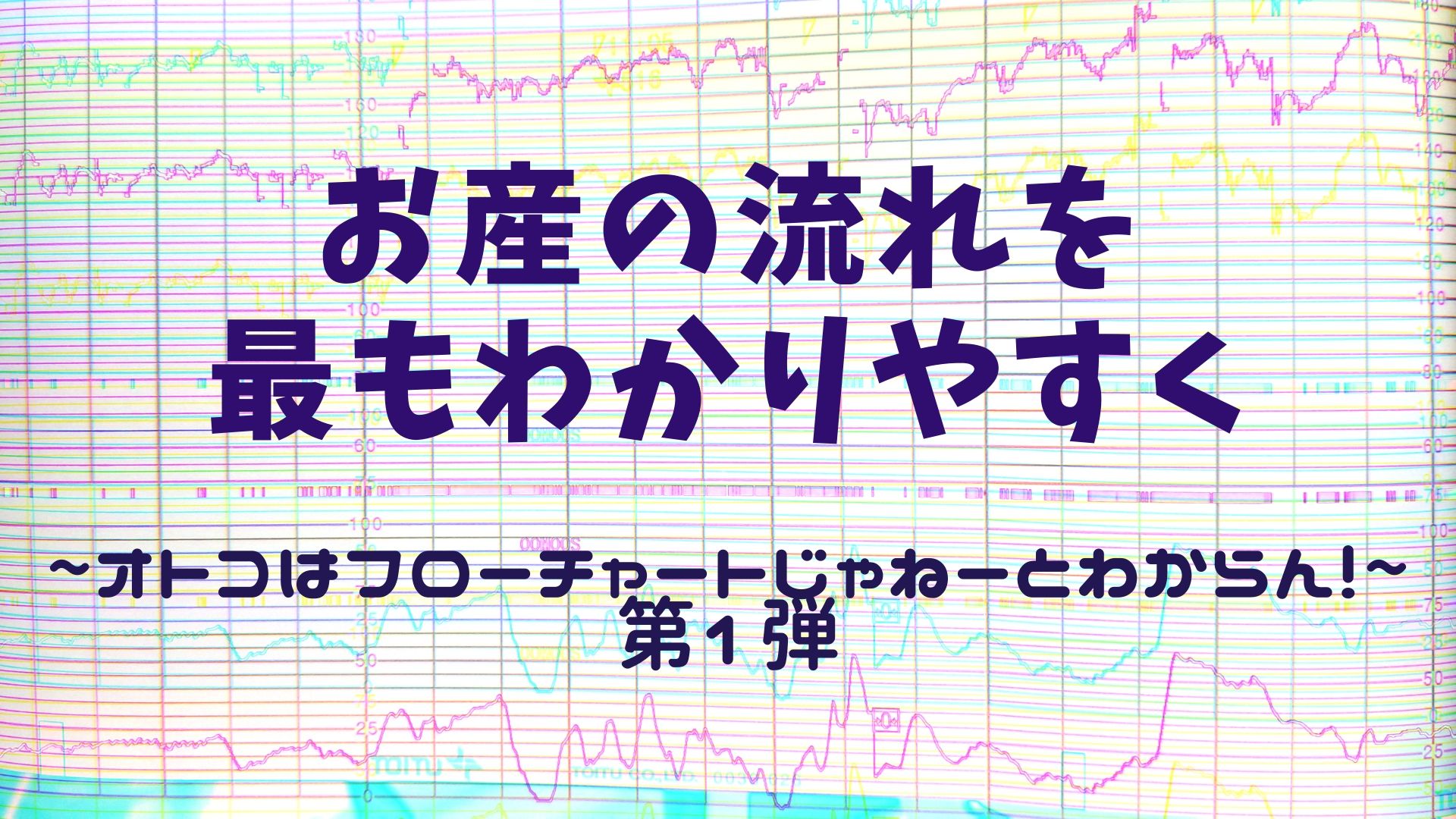資格取得のために私を動かした一言
不合理な人事評価の「定性割合」を少しでも減らす
サラリーマンとしてはベタな悩みですが私も思うことがあります。
…会社に不当な人事評価を受けていると。
営業担当だった時期も長いので、数字で判断できる実績「定量評価」にはそれなりに納得がいっています。
まぁルートセールスの会社なので、例えば数字が出やすい取引先を担当している他の人がズルい…と思うことはよくありましたが、ある程度は致し方ない事なのかと思います。
ただ強いて言うなら、元々の目標が高すぎるので、営業担当は皆(もちろん私だけでなく)事務担当と比べて定量評価が下がってしまうという不可思議は存在しました。
…では一体どのようにして営業担当はキャリアアップしていくのか。
それは、数字や形に表すことの出来ない「定性評価」です。
そのためうちの会社は、営業担当にはこの定性部分の評価を高くしてあげるという暗黙の了解がありました。
(このウチの人事評価制度の実態がそもそもどうなんだという話もありますが…)
しかし私はこの定性部分にも不運と不遇がありました。
(と少なくとも自分は思っています。 自惚れと負け惜しみなのかもしれませんが…)
若気の至り…と言ってはなんですが上司より「お客様」や自分なりの正義を優先して評価者の心証を損なったり(不遇)、人事異動で不意にアウェーの分野の部署に配属になった結果のミスが「経験」ではなく「年齢」で評価されてしまったり(不運)。
いえ、もちろん自身の落ち度に起因することも少なくないのですが、「なんだかなぁ…」と思うことばかりでした。
所属トップの一言
一度評価面接の際に自分のチームのトップに聞いてみたことがありました。
この時のトップはウチの組織には珍しく「第三者目線」「公平感」が強いと感じる方だったので、敢えて直接的に「自分が報われない理由」について聞いてみたわけです。
本当にいろいろなアドバイスをもらいましたが、それでも特に印象に残ったのは次の言葉でした。
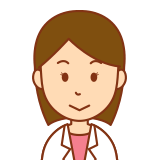
「Sくん(しかも私より後輩)は、早くしてFP1級の資格を取ったそうだよ。 君も自分の仕事に自信があるにも関わらず自己評価と他者評価が合ってないというのなら、例えば誰の目にも明らかな成果(今回で言えば資格)を武器にするのも一つの方法じゃないのかな」
…ハッとさせられました。
近しい同僚達(同期、なんならあまり離れていない先輩にも)に負けているつもりは一切なかったけれども、少なくともSくんにあって自分にないもの、いわば自分がSくんには負けているという確固たる根拠を提示されてしまった気分でした。
資格取得を定性評価と呼んでいいものかは微妙なところですが、ウチの会社においては少なくとも項目上そちらの方にありましたし、Sくんも活用したそれは「見えない努力を見える結果にする」確実な方法の一つと思ったのです。
この時から私は資格取得にチャレンジすることに決めました。
また、挑戦する資格の選定条件は以下の通りとしました。
- ウチの会社の推奨資格であるもの
- 一定程度はレベルが高く、なるべく保有しているウチの職員が少ないこと
- それでいて短期間で複数種類取得できること
実際に選定した資格、またその挑戦スケジュールについてはあとでまた触れることにします。
私の「資格」に対する価値観
勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし
私は世代や性別にしては珍しくプロ野球ってヤツに全く興味がなかったんですが(この話もどこかで語りたいです…)、
いつだったかどこかで聞いた野村克也元監督の名言で好きな言葉があります(本当は歴史上の人物の言葉だったりしたかな?)。
…今年の2月にご逝去され、先日のバラエティテレビ番組アメトーーク「ありがとうノムさん芸人」を見てふと思い出しました。
「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」
負ける時には必ず負ける理由・要素があるけれど、一方で勝つ時には理由のない勝ちがある。
何かの勝負に勝ったとしてもそれは偶然拾った勝利かもしれないから、慢心することなく次の勝負にも勝てるよう努力しなさいという意味です。
(もし違っていたらすみません…)
きちんと自分を戒めるためにもたまにこの格言を思い出しています。
…ただこれを資格取得に置き換えて、勝利を合格、敗北を不合格と捉えるとどうでしょう?
格言の本来の趣旨とは離れてしまうことは重々承知していますが、考え方が大きく変わるポイントがありませんか?
それは何かの勝負は多くの場合「次の勝負」があるのに対して、資格取得は一度「勝って」しまえば同資格については次がないということです。
もちろん更新制の資格(定期的に試験があるもの)や、TOEIC○○点(さらなる高みを目指さなくてはいけないもの)…なんてのはあるかもしれませんが…。
少なくとも私が取得を目指す資格にはそれがほとんどありません。
(更新はあるが試験ではなく定期的に講習を受ける等の単位取得制のものなど)
これを上手く活かせないかなぁという話です。
いえ、もちろんわかっています。
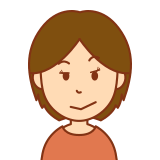
いくら資格があっても、「実力」と「経験」がないんじゃねぇ。
…そんな声が聞こえてきそうなのも。
また、例えば医療関係や危険物の取り扱いなど、絶対に中身のないものであってはならない分野の資格もたくさんあるだろうと思います。
ただ私が目指す分野と目的においてはそうとも言えないんじゃないか、そう思うのです。
以下、少し語らせてください。
“エバリュエイタビリティ” としての資格
ひと昔前から、「エンプロイアビリティ(employability)」という言葉を聞くようになりました。
つまり文字通り「雇用され得る能力」のことで、Employ(雇用する)とAbility(能力)を組み合わせた言葉のようです。
一般的には転職・再就職できるためのに有利になる能力を示すといわれています。
また、現在の組織に雇用され続ける能力の事も言うようです。
大きく見れば私はこのエンプロイアビリティを高める必要があるのだと思いますが、直近のストレスを減らしモチベーションを上げるためにはそれをさらに少し狭める必要があると感じました。
それが “エバリュエイタビリティ(評価され得る能力)” です。
evaluate(評価する)とAbility(能力)を組み合わせた私なりの造語です。
もちろんこれには今まで私が嫌いだった所謂「ごまをする」能力だったり、ラッキー(運)も含まれるのかもしれません。
でもやっぱりそれらはどうにも曖昧で、確固たる基準がないことにモヤモヤしてしまいます。
だから私は “エバリュエイタビリティ” の中でも特に形に残る成果を得ることを目的に、資格取得を目指そうと思っています。
開き直ってしまえば、私は例えば「資産運用相談のお客様により的確なアドバイスをするためにマネー系資格を取る」のではなく、人事評価のために取るのです。
お客様からしたらそんなヤツに相談したくないと思われるでしょうか?
…でも私からしたら逆に「私はこんな資格を持ってるからなんでも聞いてください」という営業マンの方が信用ならない時もあります。
そもそも資格試験って、100点満点じゃないと合格扱いにならないものなんてほぼありませんよね?
資格を武器にしてる営業マンも、もしかしたら合格基準6割の試験をギリギリで通過した人かもしれません。
それに多くのビジネスシーンにおいて有資格者がお客様の相談に回答する際、「お調べして改めてご案内します」とするケースも多いですよね。
どんな分野においても関係知識の量は膨大ですし、なんなら時代と共に随時更新・改定されてしまい追いかけるのも決して簡単な事ではないかと思います。
もともと資格はあくまでベース、「基礎知識」を得る程度のものだと思うのです。
…だから私は敢えて格好つけずに、「評価される」ために資格を取ると宣言します。
今後の動き
取得を目指す資格
これまでの話を元に、またプロフィールの補完の意味も含めて実際に私が取得を目指す資格とその理由を紹介しておきたいと思います。
「取らぬ狸の皮算用」感も否めませんが、ここに書くことで逃げ場を無くす意味もあるのでお許しください。
ファイナンシャルプランナーとしての資格。
タイトルにも入れている以上正直こちらは外す訳には行かないと思っています。
同レベルの金融財政事情研究会のFP業務検定1級ではなく、FP協会のこちらを選定した理由は「部分合格」があるからです。
(逃げもあるかもしれませんが、今回は「資格の複数取得」に重きを置いている以上、万が一の不合格続きでそれまでの時間を無駄にしてしまう[もちろん多少知識は残ると思いますが]可能性を少しでも減らしたいと考えました)。
ちなみに前段のFP業務検定2級 / AFP資格については現職の兼ね合いもあり取得済。
また、実は6科目合格が必要なCFP試験において試しに受けた「相続・事業承継設計」「金融資産運用設計」の2科目も合格済なので決して手の届かないものではないと信じています。
これは正直言って、今回目指す中では一番ハードルが高いかと思います。
内容だけでなく、講習を受ける必要があったり、1次・2次試験と取得になんなら数年かかってしまう可能性がありますし、受講・受験費用もぼったくりレベルです。
選定理由は受験資格である実務経験の中に自分の仕事も含まれている事(正直、個人相談が中心の私の業務とだいぶ離れている気がしますが…)と、企業分析に強い兄(会計士・税理士)に学習面で頼れるかもしれないと思った事です。
こちらは本当に長い目で(数年越しの資格だからこそスタートを早くしなくてはという気持ちもありますし)追っていこうと思います。
いわゆる「宅建」試験。
厳密には専門外ですが、個人資産運用相談を語るうえで「住宅ローン」は外せません。
不動産業者の方と絡む機会も多かったですし、実務に必要とされるケースも多くあります。
また、こちらは現職においても(悔しながら)実際に保有している職員も少なくありません。
全く畑違いの資格も取りたいなと思い選出しました。
テキスト見ただけで目眩がする程の暗号文ばかりでしたが、SEの友人からも、多くの人がだいたい入社前か1年目で取得させられる登竜門的な資格と聞くので、不可能ではないと信じています。
一応「FinTech」への対応を見据えて金融分野となんとか結びつけることもできますしね。
余談ですがウチの会社も最近「IT戦略部」なんて大層な部署を作ったくせにこの資格を持っている職員が少なく、武器にできるチャンスとも思っています。
ちなみにこの資格は専門外で自信がなかったのと、CFPと同じ理論で、わざわざ金をかけて研修+試験(実質部分合格)午前試験免除をもらっています。
以上が現状私が目指す資格です。
少し無謀に見えるかもしれませんが、難易度・効率・スケジュールの全て中庸をとったつもりです。
まとめ
…いかがでしたでしょうか?
私の「資格観」、伝わりましたでしょうか?
最後は少し具体的な目標にまで触れさせていただきました。
今度はさらに具体的なスケジュール設定なんかも紹介したいと思っています。
これらが吉と出るか凶と出るか。
みなさん是非、吉と出れば参考に…もし凶と出れば「しくじり先生」にしてください。
それでは。